【淨寶 1928(昭和3)年1月1日発行分】
大乗仏教は活動主義なり(6) ―境野黄洋―
●「法然聖人と時代の欲求」③
「あの全盛の平氏が、昨日今日に斯くなろうとは」というのは、すべての人の感じであったでありましょう。「祇園精舎の鐘の声、諸行無常の響あり、沙羅双樹の花の色、生者必滅の理を現す、驕れるものは久しからず、終に亡ぶる習いなり」と、『平家』の作者が歌い出したのは、誠に、当時の人々の感じを、能く現したものでありましょう。京都に残されました一門の遺族は、今日は屋島の戦、明日は壇ノ浦と、評判を聞き、一ノ谷では誰それの討死、どこそこでは何某の戦死と、聞くだけでも胸はつぶれ、伝聞の都人士も、陰ながらの涙を絞ったことでありましょう。人世は無常、世相はままならぬが常であると、嘆ぜぬ人もなかったことと思います。法然聖人の念仏教は、この時代に現れたのであります。自らこれ時代に適合したものと見ることが出来るでありましょう。殊に当時の武士は、敵も味方も、敗れたものは、身の不運をかこち、運命の恐ろしさに悶え、勝ったものでも、人を傷つけ、人を殺し、直接讐でも仇でもないものを、武士のやむなき浮き世の掟で殺したという。自省心は非常にその心を苦しめたもので、いわく菩提の念しきりに、心を動かしたものであります。平重盛が、囚われの身となり法然聖人の教えを乞うた時の、聖人の答書には、「御栄華昔も今も異事なき御身也、然れども有為のさかいの悲しきは、いまだ生をかえざるに、かかる憂き目をご覧ずるうえは、穢土はうたてき所ぞと、憂いに思し召し捨て、ふかく弥陀の本願をたのみましまさば、ご往生疑う有るべからず」とあるのであります。戦場で多くの人を殺めた人は勝った後でも、「浮世のしがらみ、已むなき義理で、人の命は絶ったけれども、元来一人として、仇も怨みもない人である、まことに気の毒なことであった。この世は思うにまかせぬ娑婆、死んで死に損、活きたは活き得という筈はない。死んだ後は一連托生、必ずや手をとって、娑婆の昔を笑う時がなくてはならない。」鎌倉の武士は、みんな斯う思ったのであります。そうしてこれは鎌倉の武士ばかりではない。今でも、人世は、実はこんな戦場で、常にお互いに戦い合い、斬り合っているのではありますまいか。罪なきものが虐げられ、善良の人が苛まれているのではありますまいか。これでは、現世の審判は、割り切れない。未来主義はここに根ざしている。人生を深刻に見た人の、否定できないものであります。
●親鸞聖人の逆戻り
この未来往生説は、法然聖人の滅後において、解釈の相違から、多くの派別を生じています。しかし正念往生は一つであります。長楽寺の隆寛律師という人は、臨終断無明と説いて、臨終に無明を断じ、立派な心になって弥陀の来迎を受けるというのであります。
九品寺の覚明房長西上人という人は、臨終発定往生と申しまして、臨終の時に、禅定に入ったような心になり、来迎を受けるのだと申しました。これらは異派の説でありまして、大体唯今の心のままで、唯念仏を一心にして、来迎を受けると申すのでありますが、要するに正念往生の解釈なのであります。ところが真宗の親鸞聖人は、この臨終の正念往生に反しまして、臨終往生の説を否定して、平生往生を主張したのであります。往生ということは、臨終の時にきまるものではない、平生の時にきまるのであって、信心を得た時が、往生決定の時であるといい、「死に際」ということを、一切重く見ないという立場を取ったのであります。これが平生業生の説なのであります。これは未来主義の中でも、臨終から平生に逆戻りをして、信心を得た平生の時から、生活上に新生命を与えられるので、本当の生活はここからはじまると言って、現実主義をここに開いているのであります。それでありますから、信心獲得の我々は、お釈迦様のあとに佛になると予定されている、いわゆる補処の弥勒菩薩のようなもので、もう成仏するに決まっているものである菩薩である。信仰の上に生きる、極楽の生活を、この世で営むものであると説いているのでありまして、「有漏の穢身はかわらねど、心は浄土に遊ぶなり」と和讃にあるのはこれであります。「極楽の生活を、この世で営む」これが「補処の菩薩の生活」というのであります。親鸞聖人は斯くの如くして、臨終から平生に引き戻し、逆戻りをして、未来教の中に、現実主義の教義を開いているのであります。
ー(了)ー
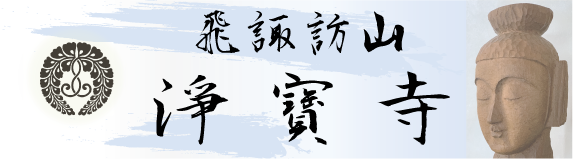





コメント