【淨寶 1928(昭和3)年5月10日発行分】
大無量寿経について(7)ー臼杵祖山ー
自力聖道門の歩みは、自分というものを段々清めて身をただし、行いを正しくして三業の所作を慎んで進み行くという。これは即ち第一歩が自分を善人聖者として踏み出したのである。しからばそれが最後まで、それで行けるかと言えば、実は最後は全くの凡夫足らざるを得なくなるのである。故に最後に廓然大悟に達する時は、これを無学というのである。そうしてそれに達せんとする道程にある間を有学というのである。自力聖道とは普通には自分の力に由りて自分を建設修成して行くことであると思われるが、その実は自分の凝結せる執着を漸時に研磨して、いよいよすりつぶしてしまい、何に一物をも留むべきものなきに達せんとするの道中である。これが自力の真実道である故に、悟りおわれば全く仏々平等である。それは大無量寿経にては師仏として説いてある世自在王如来を、龍樹菩薩はかえってこれを、弥陀の弟子としての意味を表し、
「この諸仏世尊現在十方の清浄世界に皆名を称し阿弥陀仏の本願を憶念することかくの如し」
と述べて、弥陀の念仏易行の道に由って無上正遍覚を得られた意味を表してある。元来自力の自とは自分の目をすりつぶすの意味である。自力で進んで進んで至り極まりた境地を無我の他力というのである。そこで自力は結局他力に達するまでの聖道権仮の方便である。これについて親鸞聖人は自分の信仰の道程を述べて、
「凡そ大小聖人・一切善人、本願の嘉号を以て、己が善根とするが故に、信を生ずる能わず、仏智を了せず、彼の因を建立することを了知すること能わず、故に報土に入ることなきなり。ここをもって愚禿釈の鸞、論主の解義を仰ぎ、宗師の勧化によりて、久しく、万行諸善の仮門を出でて、永く雙樹林下の往生を離れ、善本徳本の真門に廻入して、偏に、難思往生の心を発しき。然るに今、特に、方便の真門を出でて、選択の願海に転入し、速やかに難思往生の心を離れて、難思議往生を遂げんと欲す。果遂の誓、良に由あるかな。 ここに久しく願海に入りて、深く仏恩を知れり。至徳を報謝せんがために、真宗の簡要を摭うて、つねに不可思議の徳海を称念す。いよいよ斯を喜愛し、特に斯を頂戴するなり。」
と聖道権仮より浄土真実に進み、浄土門中において、三転して選択摂取の第十八願海に入りて難思議往生を遂げらるるとの意趣が信甞され、また二巻鈔(愚禿鈔)には逆転の四位を分けてその意味を表してある。広文類には能入の機位について聖道浄土の順転廻入を明かし、二巻鈔には所入の法位について浄土聖道の逆転進出を示してある。この両書の順逆入出を一聯するに、これを要するに、初め聖道自力門より入て修行し菩提をひらく道に入り、次に浄土門中の第十九願の諸々の功徳を修する行から、次に第二十願の諸々の徳本を植ゆるに進む。その中聖道の三僧祇百劫の修行は論するまでもなく、第十九願は諸善万行を修するにぎやかさではあるが、その内容が未だ充実していない。第二十願は行体は称名一行であるが、第十九願に比較すれば内容が充実して豊富である。ただ、力味のある廻向心は係わるだけが玉に瑕とでも言わるるのである。それは植諸徳本という、即ち「本願の嘉号を以て己が善根となす」という善人気取りで称名一行に依り、至心廻向欲生とお助けを仰望請求するのである。いわゆる正因自力摂生他力といい、又は心存助給口称南無阿弥陀仏という分際である。
これはその表面の当相から見て、また進趣の行位から見て、一面その止むを得ないとしても、ここに私達の注意を払うべき一事がある。それは第十八願純真なる他力の意義を宣説する真宗の内にも、似て非なるものがる。それは或はそれ自身として判然と左様には思っていないかも知れないが、しかしながら、その心持ちは知らず識らず、暗暗裡に、やはり正因自力摂生他力的になっている者が多いようである。それは単に信仰上より言えるばかりでなくして、学問上からでもある。その意味はいくらお慈悲でも、信ずるだけはこちらの力を待たねばならぬ。また、聖道門は自力だと言うても、釈尊の出世もなく、または随ってその説法がなかったならばどうすることもできない。だから自力と言ふても、釈尊という仏宝なり。教法という法宝なり。大衆という僧宝なりの他力を仰がねばならぬ。また他力と言ふても自ら信ずるの力がなければならぬ。そこで自力といい、他力といい絶対純一なものはないのであるから、完全に言い表せば、正因自力摂生他力とでもいわれる意味において、それが究竟するのであると考える者がある。
第十九願の修諸功徳の行者、又第二十願の植諸徳本の行者にしても、第十八願を捨てて見ないのではない。がしかし、夫々の至心発願欲生なり、至心廻向欲生なりの色眼鏡をかけて第十八願を見る時は、第十八願の三信十念が、かの自力執情に映じて、それが全く自力的の三信十念となるのである。親鸞聖人は、「万行仮門を出て」といい、又「特に方便真門を出て」といえるは、完全に自力執情のの色眼鏡を取り捨てて、速やかに「選択の願海に転入す」と第十八願に直面せられて、涅槃真因唯以信心の唯心独奪の真意を味わわれたのである。然るに悲しいかな今日では、兎角に聖人を一つの偶像としてしまったために、したがってその聖人の内在心味までも偶像化して一種概念としての表現に過ぎない、全く生命なき死灰物として取り扱うに至ったことである。懐うに、幾百年間の星霜を経過し、種々な時代の変遷なり影響なり境遇なり、それを後人の各々の自己執着の好餌として、又好奇として、そのさま殆ど敬虔な態度を以て尊崇するが如きかと見れば、或はまた頗る軽忽な振る舞いを以て翻弄するが如きかと思われるまでに、真の生命を失わしめられた一面のみが、最も哀れに立ち燻っているという状態である。
親鸞聖人は一切において全然力なき人であった。それはいわゆる無抵抗主義などといえる、自ら有する力を抑圧して一種の主義にからまるのではない。弾くべき何らの力の少量だも持たない、真実愚禿そのものである。これによって聞其名号信心歓喜とある経文に対して、聞かぬはならぬ信ぜねばならぬという概念化する能力さえもない聖人であった。ここにおいて初めて聖人の第十八願が開けたのである。それは聖人が最後に第十八願の真面目に立ち還えられた時は、称えて参ろうという利巧さも、諸善万行を修する尊さもないばかりでなく、聞くということも聞き得ない、信ずるということも信じ得ないところの愚禿であられたのである。それは今更初めて愚禿になったのではない。元来智目行足の欠けたる凡夫、願体戒手の叶わぬ衆生の、大馬鹿者に立ち還えられたのである。自分で聞いて信じて助けてもらうのではなくして、自分は聞く力も信ずる力もない、ただ如来のよきおはからいによって、助けられざるを得ない、全く自力無効、否、自力というものを持ち合わせないのである。
ー(8)へ続くー
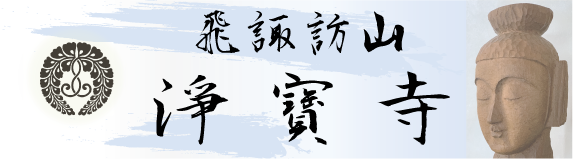





コメント