【淨寶 1927(昭和2)年12月10日発行分】
「開眼の」夕 ー藤秀翠ー
迦洞無塀氏の製作せられた聖徳太子の陶像の開眼の集いに招かれて、月の十七日の夕、浄寶寺に赴いた。如来の寶前に端然として立ちておわす白磁の神々しい太子像の前に人々と共に跪座して、まず「嘆仏偈」を拝読し、それから「皇太子聖徳奉讃」の十一首の和讃を静かに読誦したてまつる。そうして、
あはれみかぶれるこの身なり
一心帰命たへずして
奉讃ひまなくこのむべし
という一首に至った時に、あやうく涙が滲んできた。親鸞聖人の聖徳皇太子に対する敬慕と感戴とは、ここにいたって絶頂に達している。太子と聖人の魂がしっくりと抱き合って、不可思議悠久の信の世界を人々のこころに開きたもうように感じられる。
迦洞氏は以前に三尺ゆたかの観世音の立像を製作して人々の注目をひき、今また太子の尊像を成就して、その不断の精進と成長とを示された。それはこの太子像の勧請者たる諏訪氏にとって大なる満足であり、悦予であるとともに、迦洞氏を知れる全ての人々の喜びである。いや、何よりもまず作者自身の深い悦びでなければならない。
一つの芸術品をつくりあげるということは、実に並大抵のことではない。人知れぬ泣血の思いと陣痛の苦みがその裏面に伏在する。それを思う時にその作品の成否善悪ということよりも、むしろその製作に対する作者の主観の動きに共感を強いられずにはおられない。こういう点において、礼拝の対象としての太子像を生み出す作者の苦心と述懐とは、そういう芸術の分野について殆ど無眼人に等しい自分のこころをも深く動かさずにはおかないものがある。
その夜、人々の卓上の談話は趣き深いものであった。日本洋楽界の先達である永井建子老先生の音楽についての苦心談も面白く聞かれた。自分のような洋楽についての無耳人の耳にも、色々の深い響きをあたえずにはおかない躍々としたお話振りである。
耳に訴える芸術と眼に訴える芸術と、それから文字による芸術との相違、そういうことも今更のように考えさせられた。
芸術精進の一路は無涯であり無辺である。芸術に対するわれわれの欲望と願求もまた無量無辺である。
『華厳経』の善財童子は、南方遥かに五十三人の善知識をたずねて、一刀一刀自らの魂に深い聖痕を刻んでいった。人生は短し、芸術は永しと昔の詩人はうたったが、本当に人生の短さと慌ただしさとをひしひしと感じさせられるこの頃の自分である。自らの深い願いの一分をも、本当に表現することの出来ぬ恨みを懐いて、多くの芸術家はこの世を去ってゆくのではあるまいか。
累々と我が前に立つ峠かな その峠ひとつひとつ越えつつ
これは頃日、楽焼きの茶碗に迦洞さんに山を書いて頂いて、その後にわたくしの落書きした一首である。
(昭和二年十一月十九日の夜半に備後の照林坊にてしるす)
―(了)—
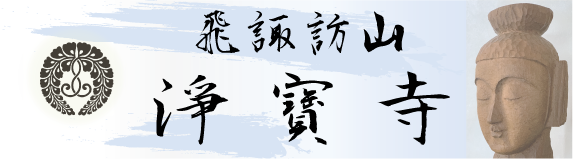





コメント