【淨寶 1927(昭和2)年10月10日発行分】
講演断片(4) 歎異抄に就いて -足利淨圓-
※この断片は第三回特別講座(昭和2年5月28・29日)のお話を載せたのであります。全く先生の校閲も経ないものであることをおことわり申します。諏訪令海
宗教には罪悪観の伴うことは言うまでもないが、親鸞聖人の罪悪観は、我々が普通考えるような部分的のものではない。聖人の罪悪感は常に生死の文字で顕されてある。これは詳しくは生老病死のことで、換言すれば迷うていることである。人間のみによって見得る罪悪観は部分的のものである。仏の真実智慧の眼から見られたら、凡夫の罪悪は決して部分的のものではない。
宗教的に考えたら、はたしてこの世に善人があろうか。親鸞聖人の心持から言えば、真実の善人と言えば仏さまより外にない。普通我々は何によって善悪を言うか。それは倫理道徳がその標準である。猫の中には猫の眼から見れば、色々違った種類があるのであろうが、人間の眼からは要するに全部猫である。難波大助は裁判官の前には大罪悪人であるが、聖人の思想から言えば、大助はもちろんであるが、それと同時に社会組織を同じくしている我々にも充分その責任がある。聖人の『教行信証』信巻に「一切の群生活、無始よりこのかた乃至今日今時にいたるまで、穢悪汚染(えあくおぜん)にして清浄の心なし、虚仮諂偽(こけてんぎ)にして真実の心なし」とある。だから、あれも罪これも罪悪と自分の罪を数え立てて、その時分の感じが深くなったところに仏の救いを感ずるように思うことは、凡夫の大きな高上りである。仏の完全なまことに接して、初めて自分の不完全の罪悪を知ることができる。仏が分かったところに自分がわかるのである。
無常ということに対しても同じことである。「今日は無常をとりつめてご縁にあいに参りました。」と言うて、茶を飲み、莨(たばこ)を吸いながら話すのです。そんな態度では、たとえ分かってもそれはただ理屈が分かったというだけで、死の一つさえ、本当には分からぬ。これらは皆迷いが根本になっているので、即ちこれほどの大事なことが平気でいられることが、即ち迷いであり罪悪である。無常と罪悪と別ものではない。無常に目覚めることのできぬ、ありったけが大きな罪悪である。
〇
ある市の警察署長さんが、ある聖者のお話によって「我々は常に罪悪を犯しているのである、署長の職を奉じていることにも、本当に目覚めてみれば、ただ月給を盗んでいるに過ぎぬ、あれも罪、これも罪悪である。」と聞かされて大いに感じ、遂に署長の職にじっとしていられなくなって、その聖者と同じ様に紺の筒袖を着て、町の掃除を始め出した。何で生活の資を得るかと言えば、よその手伝いなどをしてやっと食うて行く。これで初めて清い生活に入ったと喜んだが、一面にはこれではいけないと、真の落ち着きが得られない。苦しみ悩みが絶えぬ。自分一人なら良いが奥さんや子供がある。昔と変わった小さい室に一緒で、しかも日々食うことが用意でない、随分困る。妻子は元の生活へ帰りたいと望むが、本人は「自分は今善の生活をしている。元の罪悪の生活に帰ることはできない。」と心を責めては自分を励まして行かれるが、一方では、それがために妻子は犠牲になって、その実助からぬはめに陥っている。それで主人はどこどこまでも「自分は善いことをしている。」という心が離れない。
自分は正しいという考えには、余程危ないものがあることに気をつけねばならぬ。フランスの王様は、「自分は正しい政治をしている。」という考え方をして、自分に背く者を不正者の名のもとに、二十万人も殺して大きな恐ろしい罪悪を犯した。それはフランスの恐怖時代のことである。
この「自分は善い、正しい。」と思うことが如来の真実から見れば、一つの我慢に過ぎぬ。真の罪悪観は、仏の心に眼をつけると、この自分のありったけが全部役立たないことに目が覚めるところにある。しかも、この役立たない一々を仏の真実心によって、一つひとつ抱いていて下さることが分かる。そこには真の念仏が生まれる。
信巻に曰く「如来、一切苦悩の衆生海を悲憫(ひみん)して、不可思議兆載永劫(ふかしぎちょうさいようごう)に於て、菩薩の行を行じたまいし時、三業の所修、一念・一刹那も清浄ならざる無く、真心ならざる無し。如来、清浄の真心を以て、円融(えんにゅう)・無碍(むげ)・不可思議・不可称・不可説の至徳を成就したまえり。如来の至心を以て諸有の一切煩悩悪業邪智の群生海(ぐんじょうかい)に回施(えせ)したまえり。」
―(了)―
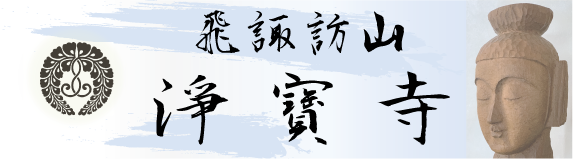





コメント