【淨寶 1927(昭和2)年9月1日発行分】
救済の宗教(2)―新宅博雄―
●救済の体験
われなくも法はつきまじ和歌の浦
あをくさびとのあらんかぎりは
これは、親鸞聖人がお亡くなりになる少し前、伊勢の西念房に与えられたお歌であるが、これは地上に人間のいる限り、救いの御法は永久に亡びないということを仰せられたものである。宗教とはさきに述べた如く、肉体的には無常、すなわち亡ぶべきもの、精神的には罪悪、すなわち自ら神聖なる能わざるもの、つまり無常と罪の上に立つ不安の存在である。
したがって、かかる人間が自ら目覚めて宗教を体験せんとする時、自証教に入らずして、救済教に入ることは自然な事である。吾人の言わんと欲するところを率直に言うならば、無常と罪悪の上に立つ不安の存在たる人間は、一度宗教的に、向かいたる時は、いかにしてもこの救済教に依らなければ、決して解決のつくものでないと言うのである。
さて、仏に救わるると言うが、そは如何になる事であろうか。救済の体験とは如何という問題である。大体、、宗教の体験は、冷暖自知で、そを体験して、初めてその真相は分かるものである。が、今しばらく、言うべからざるの世界を出来るだけの程度において、味わんとするのである。
中国の善導大師は、阿弥陀仏の救済の体験相を二つに分けて示されてある。「自身は現に是れ罪悪生死の凡夫、曠劫よりこのかた常に没し、常に流転して出離の縁あることなしと深信す。」と言えるが一つ、而して、「彼の阿弥陀仏の四十八願は衆生を摂受したまふこと疑なく慮なし。彼の願力に乗じて定んで往生を得と深信す。」と言えるがその一つである。前者は機の深信(信機)と呼ばれ、後者は法の深信(信法)と言われている。これは二種深信と言うのであるが、こは信仰或いは体験と言う直接経験としては、二の別個のものがあるのではなくして、二種は一具で、一信心である。しかもこの信機信法は、法体成就の一南無阿弥陀仏の成就の中に価値として成ぜられてあるのである。
よく、入信の方法として、無常観、罪悪観、無明観など言うが、まことに当を得た言い方であると思う。救済の体験を、人間の立場から言うならば、「我れ」が宗教的に燃焼し、その頂点に達し、無常、罪悪、無明の上に立てる自我そのものが、一時間も、否一刻もそのままに、捨ておくことの出来ない境地に至れる時、ここに仏教の摂取―救い―に与れるのである。西田幾多郎博士は、智をつくし、情をつくし、意をつくして、しかも信ぜざらんと欲するも信ぜざるを得ずして、信ずる。これ宗教の本質であり、真の体験なりと言われてある。
この救済の体験を、阿弥陀仏の方から言うならば、名号回向である。宗乗学の見解に立ちて味わんに、この人間に与えられる名号とは、法蔵菩薩の願行そなわれる「摂諸善法具諸徳本」の名号で、この一法さえ与えられるならば、人間の救済、浄土往生の全体は満足せられるのである。
この名号は、そが出来上がる動機なり、目的なりは、ただ一切の罪と無常との不安に立つ吾人を、救済せんがためなのである。大無量寿経の修行段と言うところには、「令諸衆生功徳成就」と述べられてある。動機目的既にかくの如きものであるから、仏は我々凡夫が、最も安易にいただけるように、仏より巧みに働きかけてくださるのである。
すなわち、光明無量、寿命無量の覚証を、南無阿弥陀仏の名号の中におさめて、いわゆる乗名示現して、その名を吾人をして念持せしめて与えられるのである。本願成就文には、「聞其名号信心歓喜乃至一念」と信の意義において、救済の体験があらわされてある。その名号が、吾人のものとなるは如何になるか、これはあまりに分析的なようであるが、善導大師の玄義分の六字釈は、これに明快なる解釈を与えている。
親鸞聖人は教行信証の行巻に於いて、この六字釈に対して綿密なる考察をなされ、而して、南無阿弥陀仏の名号は、吾人に本願招喚の勅命、すなわち「マネキヨバフオホセ」として向いたまうと仰せられた。しかもこの勅命とは、名号中に内在する全てのもの、すなわち救済の心も、救済者も、施与のものも、全てを全うして、全名号を代表して吾人凡夫へ向かわるる救済意志の発表である。これ「ヨクタノメ」、「ヨクカカレ」帰せよ、托せよと命じらるる勅命であって、この勅命に依って吾人を帰せしめ、信ぜしめて、名号全体を衆生へ施与したもうのである。
この場合帰と言い、信と言うは、無論吾人よりなす自力的意味の帰でも信でもない。全く名号の独り働きで、吾人をして、帰せしめ、信ぜしめて、名号功徳を与えたもうのである。
この名号が、吾人へ信としてとどくためには、名号が内徳として持つ光明は働く。光明に摂取と調熟の二あるならば、その前者の意味において働くのである。かくて吾人にわたりたる名号は、原因となって、現実に正定聚の位に住し、而して吾人は利他円満の妙位無上涅槃の極果を得、利他教他地の利益を得るのである。
救済の体験は斯様に、吾人と仏との二つの立場より味わうことができ、その姿が違うように見えるが、そは体験の実相としては、「不安なる自己が如来に救われた」と言う一事実より外にはない。さきの善導大師の二種一具なる味わいと同趣である。
足利義山師がご臨終の際、多くの弟子たちが何か御法悦をと願った時、与えられたと言う詩が残されてある。初の二句は、「八十余年罪山ノ如シ、罪障決定無間ニ堕セン」と言うので、言わば丁度法の深信である。ひと度亡びるもの、迷うものと、行き詰れる自己。一刻の猶予ならぬだけ、燃焼せる自己は、同時にあたたかきあふるる慈愛の阿弥陀仏の摂取救済に与るのである。これは実にささやかなる人間智をもって解釈し、論究し得ざる神秘の世界であり、絶対の境地である。
体験とはその本義は、超経験を経験することだと言うが、吾人の経験界、有限界を超えた、本願、名号をとらえるのである。蓮如上人は、「弥陀をたのめば南無阿弥陀仏の主になるなり」と仰せられたが、この凡夫が南無阿弥陀仏の主になる、げに偉大なる事実ではないか。月の光で月を見ると言うが、仏の作用によって、仏に一致せしめられるのである。これぞ宗学のいわゆる他力回向の信である。プラントは国家以上のものを知るものでなければ、よく国家を支配することは出来ぬと言ったが、同じ筆法で、人間以上、人生以上の世界の力によらずんば、人間及び人生はその解決を得ることは出来ない。
この救済の体験は、二つのものを持っている。一は自我の解決、換言すれば、生死の解決である。而して他の一は一切を生かす、換言すれば、救われたる者の道徳生活である。救済の体験、こはあまりに偉大なる事実なるに対して、筆舌あまりに拙く、その真相の一分も筆にのぼらなかったかと案ぜられる。次に緒論として本編の短を補いつつ、信仰と道徳生活の交渉を見ることとする。
(了)
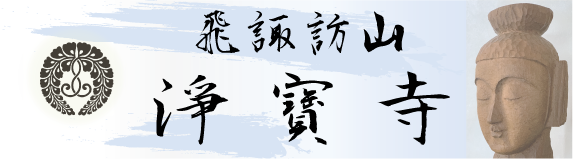





コメント