【淨寶第7号 1926(大正15)年7月30日発行分】
浄土真宗という宗教は如何なる輪郭をもっているか、親鸞聖人の宗教は仏教で如何なる立場にあるのかという事を最初に考えてみたいと思う。
先ず、日本の国で「念仏で救われる」という事を鎌倉時代に法然聖人が叫ばれた時、あちこちから非常な迫害が起こった。その主なる人は笠置(かさぎ)の解脱上人(げだつしょうにん)。もう一人は高尾の明恵上人(みょうえしょうにん)でありました。この人達は常に宮廷に出入りしていた権威のある方々であったが、解脱上人は興福寺の奏状という弾劾文に九ヶ条をあげて念仏宗を迫害した。これが原因となって法然聖人も親鸞聖人も遠国に追放されたのであります。その弾劾文の一ヶ条に「教主釈尊を軽んずるのあやまり」というのがある。なるほど、真宗の御堂には釈尊を奉じていない、ちょっと考えてみると変である。そこで法然は仏教徒という仮面を冠っているが、その実は真の仏教を奉ずるものでないと専修念仏を弾劾したのである。今頃でも、どうかすると「真宗では、なぜお釈迦さまをご安置しないのか」と尋ねる人がある。そこで、真宗という宗教は一体どんな宗教であるかを考える必要がある。
真宗は無論、親鸞聖人によって開かれたのであるから、聖人を御開山(ごかいさん)という。しかし、それは真宗が単に聖人のふところから、転げ出たというのではない。真理は無限である。この真理は客観性と普遍性とをもっている。だから親鸞聖人の宗教の本質は、源をどこに発しているか。たとえば花が咲いたといえば、一面には種子がなくてはならぬ如く、浄土真宗の源はどこにあるか。即ち教法の源流は如何(いかん)。これはかなり難しい問題でありますが、人間の世界において開かれたのは何時がはじめであるか。祖聖(そせい-親鸞聖人のこと)は明らかに「真実の教を顕さば大無量寿経これなり」といわれてある。この経は言うまでもなく釈尊が説かれたものであります。法然聖人は一切経の中から特に観無量寿経を選んだ。祖聖は沢山の教の中から特に大無量寿経を選んで真実の教とせられた。これは一体何の意味であろうか。祖聖は大無量寿経の本質として、如来の名号と、如来の本願が説かれてあるものとご覧になった。本願とは如来が我々を救わんとする救済意志であり、その如来の救済力の表現が名号である。この如来の本願と名号こそ宗教の最高であり、それを説かれた大無量寿経こそ真実の教として選ばれたのであります。他のすべての経典もみな真理に違いはないが、それは賢くなったら救われる、善いことをしたら助かるという教えである。大経はこれに反して、如来のお慈悲を受けとることが救われる原理になっている。昔からこの経には法の真実が出ているといわれている。即ち紅白粉(べにおしろい)を洗い落とした如来さまのお心がはっきりとでている。つまり、真理の全体を出してある。世間でも親の小言とか、親友の忠告などは、中々快く受けないものである。これは教えを説くものの苦しいことの一つであって、真実をそのまま受け入れることができたら、如来さまに苦しみはないのである。嘘やごまかしによって生活をしている人間に真実を説くことは中々の難事である。そこで方便が必要となってくるのである。世間に嘘も方便というが、これはあながち悪い意味ではない。嘘を言っても真実を徹底させようとすることが真実である。この意味において八万四千の方便教を説かれたのが釈尊一代の経である。
今、大無量寿経は方便の白粉(おしろい)を落とした真実の経であるとみたのが祖聖である。大経を開いてみると、この経の会座(えざ)である霊鷲山(りょうじゅせん)に集まった聴衆1万2千の聖者(しょうじゃ)のすがたを顕すに、まったく釈尊自身の八相をもって説いてある。而して説法せられる釈尊自身は、聖道諸説の常の規格をはなれて、真実に生き、全く弥陀と二而不二(ににふに)の二つにして一つの境に住されたのであります。阿難が「今日の如く輝いた世尊のおすがたを拝したことは未だかつてございません」と驚いたのは無理はない。これが即ち五徳瑞現(ごとくずいげん)の姿で弥陀と同一の境に入られたのである。この全体の模様は釈尊それ自身、大地にすべりおりて、聴衆の一人になっておられる姿であります。
宗教は真理それ自身の声をきくのである。単に理屈ではない。真理は常に自ら語るそれでないと真理は説けぬ。ゆえに語る者は聞くものでなくてはならぬ。かくしてこそ真理を表現し得るのである。
また、大経の上巻には欲生我国(よくしょうがこく)といい、下巻には願生彼国(がんしょうひこく)とある。これをよく注意してみるに、大経は釈尊が主人公であるから、自分のことを我といい、弥陀のことを彼といわねばならぬはずである。然るに、それが逆に弥陀の因位の法蔵菩薩を我といい、彼の国に行けというのが釈尊の言葉になっている。即ち、説くものが弥陀であり、聞くものが釈迦になっている。釈尊自ら説きながら、大地にひざまずいて聞いているのである。大無量寿経は釈尊の主観を通した道理ではなくて、釈尊が頭をさげて受け取った真理が表現されてある。つまり、釋尊のままが阿弥陀さまとなっている。これを、融本(ゆうほん)の釈迦といわれている。
もう一つは、この大無量寿経は、釈尊が「特留此経」(どくるしきょう)といって、この経を弥勒(みろく)に付属している。即ちすべての経が亡んでもこの経だけは亡びないという念願をこめている。この大経は永劫(ようごう)に亡びない真理がこもっているからであります。釈尊入滅(にゅうめつ)して二千年の後に現れたのが親鸞聖人であるが、それまでは哲学的に、或いは芸術的に、もてあそぶ人はあったが、真実に大無量寿経を求めた人はいなかった。親鸞聖人は謙譲(けんじょう)な人間の名によって釈尊のままを受け取ったのである。そこで釈尊の魂を見抜いた人は親鸞聖人である。この意味において釈尊をまつらないのは人間の固定した釈尊よりも、釈尊の魂、即ち弥陀をまつった方が、むしろ釈尊を永遠にまつる所以(ゆえん)である。釈尊は二千年前の応身仏(おうしんぶつ)であるが、南無阿弥陀仏の名によって、釈尊の生きた魂を安置しているのであります。
次に名号を称えるということは如何なる意味であろうか。もう一つさかのぼって阿弥陀さまは人格的である。これは私の生命と交渉している人なら有難いが、全体仏さまとはどんなものであろうか。また、どこにおられるかということが問題である。もし、それは美しい天人のような姿をしたものであるとか、中には壁に写った仏さまを見たという人があるが、それは、本当の仏さまではない。親鸞聖人にお尋ねすると仏さまというは名号だと言われてある。今、本堂にまつってあるのは南無阿弥陀仏の意味を表現したのであって、つまり浄土真宗というはお名号の外ないのである。
然らば、名号とは如何なるものであるかというに、勿論、南無阿弥陀仏であるが、これは人間の世界における認識の限度であって、人間の知識は何も分からない盲目的なものであるから、名号によって明らかにせられたのである。故に、私の分かる如来さまは、南無阿弥陀仏だけであります。然らば、如何にして名号と転化して、人間に接触してきたのであるかというに、その過程が大体三つに分かれる。絶対の一如より如来と顕れ、更に名号と表現してきたのであります。一如とは如来さまのお悟りであって、さながらという意味である。また一つは、絶対であって、因果を超越し、有無を超越し、迷悟(めいご)を超越した、真空の世界である。花を見て「奇麗だなあ」とうっとりとした時は花もなく、私というものもない。また、美しいという観念もない。この二相の世界を超えた境地が一如である。つまり迷悟有無を超えた世界を一如と名づけているのであります。梁(りょう)の武帝が達磨(だるま)に第一相をたずねた時、達磨は不空と答えた。へんてこな答えのようであるが、これが一番よい答えである。人間の頭に罐詰したような仏を見出すのでない。仏を見出す時は、一如法界身心顕とお浄土で顕れて下さるのである。一如の世界は私共は憧れてはいるが直ちにその世界へ飛び込むことができぬ。キリスト教の神秘派が欲望と言語と思惟とを沈黙したところに、神と一つになる世界があるといっている。白隠禅師(はくいんぜんじ)が女郎の誠と玉子の四角といっているが、これは人間の理屈を破産せよという事である。二つの世界を破産し、超越したところに、一の世界がある。だが、直ちに一の世界に飛び込めるなら、法蔵も阿弥陀仏もいらなかったのである。飛び込んだのと飛び込んだつもりなのとは大に異なっている。親鸞聖人はこれを知った人である。パスカルという人は「人間は考える葦である」と言った。人間というものは、理性と本能との合したものであると私は思う。我々から結婚とか、食事とかを絶対に離すことはできぬ。もし離せば人間でない。ある人が言った、「今日の若い医者は病気を治すことはうまいが、しかし、病気の治った時、人間は死んでいる」と。宗教家の中にも確かに、こんな人がある。救われるということの理屈は三角でも四角でもよい。ただこの私が救われたいのである。人間は人間のなりで救われていかなければならなぬ。親鸞聖人はそれを見出した人である。西洋に、ある青年が真理を見出したいと願っていたが、ある夜のこと、静かにベールをまとった一つの像を見出した。月は銀のように澄みわたっている。どこからともなく、静かな囁きを聞いた。「お前が憧れている真理はこれであるぞ。しかし決して、このベールをはぐる事はならん」という。それだのに青年は真理の裸体を見ようと思って、そのベールをはぐった。と同時にその青年は死んでしまった。真理は神秘の世界である。ベールをまとった世界である。直ちに一如の世界へ飛び込むことは出来ぬ。闇の存在するところに、そのままでは明かりはたえられない。明かりの存在するところに闇はたえられない。親鸞聖人は「如」が私に来るといわれた。相対から絶対へは行けぬ。絶対から相対に来たのが如来である。つまり、真理が我々の世界へ揺るぎ出て来たのが如来である。一の世界が二の世界へ表現して来た時、考えられぬ世界が考えられる因果の世界となって来たのである。即ち私を救わんとするものが如来である。
私の背後に私を呼ぶものが法蔵であり、理想の彼岸に我を召し給うものが阿弥陀仏である。
限定された世界に我を生かそうとするものは、見仏の宗教である。観仏三昧経等に大念に大仏を見るとあるが如く、直ちに仏を見んとするのである。親鸞聖人はこれもわからぬと言われた。純粋理性の聖者なら見出すこともできるだろうが、私共は理性と本能に引きずられて金を求め食を求めている凡夫である。金が欲しいような世界には到底仏を見出すことは出来ない。そこで直ちには如来の世界は分からないから、分かるように表現して来たのが南無阿弥陀仏である。ところが名号といっても、一如や如来をお浄土に忘れて来たのではない。水のままが波となっている様なものである。賢いものも愚かなものも、名号によって初めて受け入れられるのである。
勅修御伝(ちょくしゅごでん)の中にあるが、高野の明遍僧都(みょうへんそうず)が名号を称うるのみにて救われるということはないと、常に法然聖人を罵っていたところ、ある夜、夢の中に、沢山の病人がいたところへ、一人の聖者が鉄鉢に粥をいれて、堅いものや果物などは食べられないであろうと、この温かい粥をを与えた。明遍があのなつかしい聖者は誰かと尋ねたら、あれは法然聖人であるとのことであった。法然聖人は南無阿弥陀仏を称えるだけで助かると言った。我々は堅いものは、歯節に合わないから粥を与えて下さったのである。一如は人間の認識する世界ではない。南無阿弥陀仏の名によって、表現して、初めて受けいれることができる、これが名号であります。
名号の言葉ぐらいが何か、というが、決してそうではない。子供が「お母ちゃん」と呼ぶ。そこには本当の母と子が一つになっている。この「かあちゃん」と呼ぶ言葉の中に、二つの魂が一つになっている。この一つの言葉が親の写真を見るよりも、もっとなつかしい供養である。親鸞聖人が手を合わせて南無阿弥陀仏と称えられたところに、「我よく汝を護らん」と呼びかけて下さる如来の声を受けいれられたのであります。我よく汝を救うという呼び声の中に、一如法界の全体が飛び込んで来るのである。それ故、十字架のキリストや菩提樹下の釈尊の如きなら、確かな存在のように思う。しかし、あれは既に過去のものに過ぎない。今、万人の前に実現して来るのは名号より外にないのである。大無量寿経は我よく汝を救うという。なつかしい久遠の声を静かに釈迦が受けいれられたのである。教行信証の中に、沢山の経を引いていられるが、全ての経は、私の魂をよびさましている声だと、親鸞聖人が言われた。聖人は、南無阿弥陀仏の上に救いを求められたのであります。私は浄土真宗は哲学的よりも、芸術的にもっと微妙(みみょう)な声をききたいものと思う。親鸞聖人は、南無阿弥陀仏と称えているところに自分を呼んで下さる如来の声をきかれたのである。ここにおいて、大無量寿経を霊鷲山に説く時、如来さまの前にひざまずいて聞いていた釈尊と、法然聖人のもとにひざまずいて聞いた親鸞聖人とは、よく似通った点があると思う。私たちも静かに如来さまの前に合掌して、如来の声をきかせて頂きましょう。
(第2講から第8講まで紛失。次回は第9講)
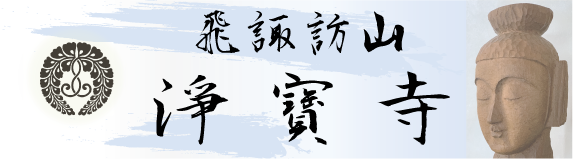





コメント