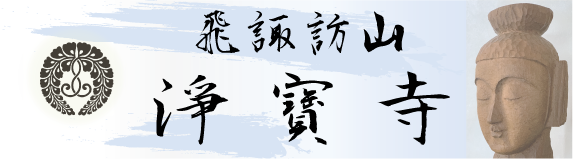管理人– Author –
-

各フロアの紹介
-

納骨仏壇
【】 新規納骨壇の運営を開始いたしました。 お問合せはこちらから 又は淨寶寺(電話082-241-1586)まで 納骨壇パンフレットHP版 納骨壇パンフレットHP版 -

素晴らしき世界
先日、公開中の映画「素晴らしき世界」を観て来ました。主演は役所広司。刑期を終えて社会復帰を目指す、中年元ヤクザの悲哀を見事に演じておられ、幾度も涙を誘われました。 (※以下あらすじ。ネタバレ注意!!) 元極道の三上は純真な人柄だ... -

平和公園レストハウス リニューアルオープン
昨年往生した前住職諏訪了我がライフワークとして長年携わり続けたものの一つに「被爆建物の保存運動」があります。特に、平和公園内のレストハウス(元大正屋呉服店)は、淨寶寺も所在した旧中島本町の中、唯一現存する被爆遺跡として、往時を偲ぶよすが... -

ANT-Hiroshima 被爆証言と医科学的解説シリーズ 第3回「原爆投下直後から約1ヵ月、救護活動に従事した11歳と13歳の少女たち」
●日時 2019(令和元)年8月24日(土) 13:30~16:00(13:00会場) ●場所 広島平和記念資料館地下メモリアルホール ※事前申込不要/参加無料 原爆投下時より、被爆者は何を見、どう生き抜いて来たのか。その貴重な証言を医科学的解説を交え... -

ANT-Hiroshima 被爆証言と医科学的解説シリーズ 第1回「爆心地から540mで被爆した少女」
【】 ●日時 2019(平成31)年2月16日(土) 13:30~16:00(13:00会場) ●場所 広島平和記念資料館地下メモリアルホール ※事前申込不要/参加無料 原爆投下時より、被爆者は何を見、どう生き抜いて来たのか。その貴重な証言を医科学的解説を... -

全戦争死没者追悼法要~前住職が法話します
来る、平成30年7月7日(土曜日)、中区寺町の本願寺広島別院において、「平和を願う念仏者の集い」が開かれます。 午前の部は「平和を語る集い」。広島平和記念資料館館長、志賀賢治氏が「記憶の継承」と題して講演されます(午前10時から)。 そして午後... -

スリランカ滞在記(42)
激しく水しぶきを上げる渓谷の急流も、やがて緩やかな流れとなり、凪いだ海へと導かれていく。 自然の摂理であります。 一昨年の九月より始まった「スリランカ滞在記」も、当初は激流の如く回を重ねておりましたが、次第に大河の流れのように緩慢な更新と... -

スリランカ滞在記(41)
前回、5月の更新から約4ヵ月。季節は移り変わり、新緑から梅雨、猛暑を経て、朝夕の風に秋を感じる今日この頃となってしまいました。もう何人も続きを期待していないであろう「スリランカ滞在記」。なぜ長期に亘り休止していたのか?その理由は闇に葬りつ... -

平和之観音
原爆投下から72年回目の8月6日を迎えた本日、例年通り「中島平和観音会」主催の「旧中島本町原爆犠牲者追悼法要」をお勤めさせて頂きました。 平和公園はかつて「中島地区」と呼ばれ、六つの町からなり、4400名の住民が生活を営んでいました。 淨寶寺もそ... -

スリランカ滞在記(40)
前回、「スリランカ滞在記(39)」において、我々一行は、ついにスリランカの魂ともいうべき「仏歯寺」を足を踏み入れ、そして、その心臓部ともいうべき「仏歯」が秘蔵されている仏殿の前へと辿り着いたのでした。 (仏歯については「スリランカ滞在記(23... -

和太鼓「いろはたまてばこ。」H29門信徒総会
去る4月23日(日曜日)、平成29年度の門信徒総会を開催させていただき、総勢52名のご参加を頂戴いたしました。 お勤め、各種ご報告と例年通りの次第を経て、お陰様で本年もつつがなく総会を終えることができました。 この後は毎年恒例の余興タイム...