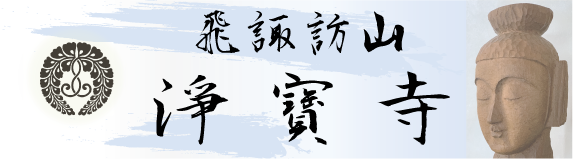新宅博雄– category –
-

柳宗悦氏の宗教論と他力救済 ―新宅博雄―
【淨寶 1927(昭和2)年12月10日発行分】 柳宗悦氏の宗教論と他力救済 -新宅博雄- 柳宗悦の思想は講座、その他の雑誌にも発表せられましたが、著書としては、「宗教的軌跡」、「宗教とその真理」、「宗教の理解」、並びに「神について」の四... -

救済の宗教(2)―新宅博雄―
【淨寶 1927(昭和2)年9月1日発行分】 救済の宗教(2)―新宅博雄― ●救済の体験 われなくも法はつきまじ和歌の浦 あをくさびとのあらんかぎりは これは、親鸞聖人がお亡くなりになる少し前、伊勢の西念房に与えられたお歌である... -

救済の宗教(1)―新宅博雄―
【淨寶 1927(昭和2)年8月1日発行分】 「救済の宗教」(1) ●人間について(宗教的主体の問題) さきに救済仏について述べた(※1)ので、今回はその救いの一要素たる人間について考えることとする。一体人間の本性は善いものであろうか、悪いものであ...
1