【淨寶 1927(昭和2)年12月10日発行分】
大乗仏教は活動主義なり(2) ―境野黄洋―
●「釈迦如来の生涯」
私は何時でも、仏教は果たして活動主義であるかないか、これを教祖大聖釈尊の生活に見るがよい、これが何よりの証拠だということを申すのであります。お釈迦様の生涯は、三十成道と申しまして、その道を得られましたのが、三十才というのでありますが―もっとも、これには歴史上多少の異論もありますが、そんなことはどうでもよろしい―とにかく、先ず三十として、これから八十才入滅まで、凡そ五十年間というものは、実に東奔西走と申しますか、中天竺の各地を、旅から旅の生活であったのであります。そうして最後の旅に於いては、途中ご病気にお罹りになりまして、非常な苦痛であったにもかかわらず、病をおして至るところ法を説かれ、とうとう鳩尸那城外の町までお出になりました時は、全く病に疲れて、お歩きになることは出来なくなり、終に鳩尸那城外の林の中で身を横たえられたのであります。この林は、沙羅という樹の林であったので、沙羅林と申します。ここに寝てしまわれました時に、そのお身体の両側の樹が両方から枝を交えて、自ら屋根を造って覆い奉ったのですが、それは伝説が段々神秘化して後に起こったものでありましょう。お弟子が悲痛に沈んで前後を囲む。多くの見舞いの人が集まる。伝説では、あらゆる動物が集まったと申しますが、この偉人の死は、天地を感動したという譬喩的伝説でありましょう。その時、この沙羅林の樹までがその色を失って白く、殆ど鶴の羽の如く白けてしまった。鶴林などと申すのは、これから起こったと申しますが、しかしこれは間違いでありまして、「大涅槃経」によると、釈尊の前後を飾るべく、この沙羅林が銀世界の如く変じたのが、その皎潔、神々しさは極楽を現じたというので、これを「なお白鶴の如し」といったのであります。白けてしまって、色を失った悲惨の形容としたのは、後の「涅槃荼毘分」という、偽経の説なのでありますが、それが却って一般に伝ってしまったのであります。これもただ一つの形容でありますから、どうでもよいのでありますが、兎に角、釈尊のご病気というので、この沙羅林は、一大悲哀の光景を現じたことは申すまでもないことでありました。それとは知らずに当時、鳩尸那に居りまして、須跋陀羅という老人がある。求道の念の高かった人であると見えまして、釈尊のここにお出になったということを聞き、特に教えを受けんがため、この林を訪ねて参ったのであります。ところがお弟子の阿難は、「今や世尊は大患におかかりである。ご入滅も近いと危ぶまれる。とてもお前にお話しは出来ない。」というような挨拶を致して居られると、釈尊は寝ながらこれをお聞きになりまして、特に枕頭にお呼びになり、須跋陀羅のために道をお説きになる。これが広く読まれております「遺教経」の中に「釈迦牟尼仏、はじめに法輪を転じて、阿若僑陳如を対し給い、終わりの説法に、須跋陀羅を対し給う。対すべきところのものは、皆既に対し終わって、沙羅双樹の間において、まさに涅槃に入り給わんとす。この時、中夜寂然として聲なし。」とある一段であります。釈尊悟後の最初の弟子、初転法輪で救済のお弟子が阿若僑陳如という人であり、最後のお弟子がこの須跋陀羅であったと申すのであります。「中夜寂然として聲なし。」とありますから、いずれ林閑とした四隣閴寂、バサとの音もない最夜中でありましたろう。既に須跋陀羅に対する説法も終わりまして、愈々多くのお弟子達に対し、最後の説法、言わば、御遺言がはじまったわけであります。この説法が、後の「大般涅槃経」というものになったのであります。この最後、御遺言の説法の要点は、どういうところにあるかと申すならば、大体先ずこうであります。「自分はもう八十という老体になった。この世の因縁が尽きて死ぬるということは、やむを得ないことである。車の輪が壊れた、もう運転が出来なくなったのである。凡そ人の世は、生あるものは必ず死し、遇うものは必ず離る。これは人間の常、今更驚くべきことはない。汝ら悲しむことなかれ。」と、こう仰いまして、それから、「第一に(弟子たちに)尋ねたいことは、我が今日まで説いてきたところの、この道において、或いは疑いの存するところはないか?凡そこの道を得る者は、永久に我を見るものである。我がこの身体がよし死んでも、我が説ける道は永久に存する。道の存するところに、我は永久に生きているのである。」―「若曹 但當案経戒奉行之 我亦在此僧中」と、「泥洹経」には出ております。「遺教経」の中には、一層適切に、「如来の法身は、常に在して滅せざるなり。」と言うているのであります。「我は死なんぞ」と、力強く遺されました。このお言葉は、後の大乗仏教にとっては非常な大事な問題となり、「法華経」では「常在霊鷲山」で、仏は霊鷲山に常住して死し給わずといい、「涅槃経」では、佛の法身は常住にして不滅であるといい、仏身常住不滅の信仰となって、大乗仏教徒の根本理論の立場を築きあげているものであります。如何にこの最後の一言が、遺弟等にとって感銘深いものであったかを知ることが出来るのであります。仏はまた「もう疑いはないが、死んだ後に、疑があったというような後悔をするな。」、「遺教経」には「佛斯くの如くとなえ給うこと三度に及ぶ。」とあります。そこでお傍におった阿莵楼陀尊者が進み出まして、「世尊、月は熱かしむべく、日は冷かならしむべくとも、佛の説き給える四諦は異ならしむべからず。」、あなたのお説きになりました、四諦の真理については、疑のところがございません。疑なきが故に問い奉らないのでございます。」と申し上げたのでありますが、やがてこれを最期として、大聖釈尊はこの世の影を隠し給うたのであります。何と尊い生涯でありましょう。八十の高齢になるまで、旅から旅と、道を説き、いわゆる一所不定の形で、一定の住所もない。そうして、歩き詰めに歩いて、最後に歩けなくなって、鳩尸那の沙羅樹林中に仆れ、最後まで循々として道を説いて止まない。そのはたらきは目覚ましいものであります。この大聖釈尊を教祖として有する大乗仏教が、独り理屈の上からばかりではない、この歴史的事実に顧みても、何として非活動的な宗教などと言われ得るでありましょう。
―(3)へ続く―
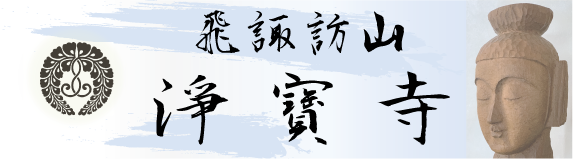





コメント