【淨寶 1927(昭和2)年10月10日発行分】
求道のとびら(1) -大内義直-
仏陀一日、弟子阿難にいいけるは、「汝、この城中に、一人の牧牛者あり、毎朝幾百の牛を追いて野外に出で、牧草を食(は)ましめ、これを養いつつあるを知れりや」と。阿難答えて曰く、「ただ爾(しか)り世尊、これを知れり」と。仏再び阿難に告げ給いけるは、「阿難、爾り、世の人は、皆悉くこの牛の如くなるを知るべし。牛は牧者に伴われ、その腹を充たさんとて、嬉々として城門を出づるにあらずや。夕には一日の食に満足して、いそいそとして城内に入り来るにあらずや。されど牛は、自分、牧者が、群羊の肥え太るを待ち、その生命を取らんとし、己が仲間の日に日に幾頭ずつかを減じつつあるを知らず。ただ牧者は己を美味に飽かしむるものとのみ思えり。惑える人も、またこの牛に似たらずや」と。仏なお語を続いて曰く、「阿難よ、時はなお牧者の如し。時の進むと共に、人はその富を得、その名を得、その位置を得、人は皆思えり、時は己をして飽かしむと。何ぞ知らん、その飽ける己の仲間は、暫時この牧者によって撲殺せられ、時によりて得たる一切の満足は、その機至れば、悉くこれを一杯の土中に埋めんとしつつある所のものに非ずや」と。
これは「法句譬喩経」の中に仏の説き給える譬喩談の一節である。
そもそも人は精神生活と共に、勿論肉体的生活を遂げなければならない。しかし普通の人情として、十中の八、九は、先ず重きを肉体的生活に置いている。肉体的生活は、物質的の快楽ということが重なる目的となるので、この目的にのみに重きを置くことになると、即ち利益欲望のためには全ての分別・判断を失うことになってくる。これが即ち利欲に目が眩んだ人で、五十年の生涯をただこの利欲のために過ごして、人生の高尚な意義も少しも理解することなく終わってしまうことになるのである。人はもとより肉体的生活をも遂げて行かなければならぬものではあるけれども、ただ営々として一生の行動を一つの墓の中に夢として埋めてしまうことは、あまりに果敢ない話ではあるまいか。人の真の道に入らんと欲するものは、先ずこの物質的生活の束縛から脱却するを以て、第一歩となさねばなるまい。
しかしながら、人は到底肉体を離れて生活することの出来るものではない。物質的欲望を全て取り去って、いわゆる寒厳枯木の様になることは大変不自然のことであり、また畢竟不可能のことである。高尚なる精神的生活ということを重んずるのは尊いことであるが、しかし肉体を強いて罪悪視し軽蔑することは、矢張り人生の一面のみを見て全体を見ない、つまり円満な見方とういことは出来ないのである。とかく人生における一般の人は、牧者に追わるる牛の如く、精神的生活を顧みないという迷惑を脱することが難しいのであって、これに反して、精神生活を重んずるという学者、求道の人、いわゆる道学者的見解では、ともすれば、この物質的生活を極端に拝するの幣がある。真に道に入らんとする者は、またこの道学者的偏見から脱するを以て、その第二歩としなければならない。
大聖釈尊がインドに降誕し給いし当時、世に行われておった九十六種の外道という、いわゆるバラモン教の中には、大体二つの区別があった。その一つは快楽派で、一つは苦行派である。快楽派というのは、即ち順生外道の類で、つまり順生は順俗派とでも言うか、世俗普通の考に一致して、物質的快楽を求るを以て人生の本面目なりと主張するところのものである。しかしかかる順俗派は、比較的類の少ないものであって、そのほかのバラモン教の諸派中の大部分は、先ず苦行派に属するものであった。苦行派というのは、純粋な精神生活に入ろうとするには、汚れた物質的生活を脱し、肉体的繋縛から離れて、本来清浄の精神をして独立せしめなければならぬというので、あらゆる手段を以て、肉体を苦しめ。物質的快楽を奪い、その欲念を絶たんとするところの宗教であって、世界の宗教には、何れも皆この意味を、多少は有しているのであるけれども、しかしその極端なる主張は、実にインド宗教の特色と言ってよいと思う。
仏陀は、吾人に二種の煩悩を有することを説かれている。一つは修惑で、一つは見惑である。修惑というのは、普通の物質肉体の誘惑によって起こすところの煩悩で、見惑というのは、学者の迷見を指したのである。
仏陀の教え給うところに従えば、吾人はこの二種の迷惑を脱し、快楽説の深坑に陥ってはならないと共に、物質的生活を軽蔑する邪路に踏み込んでもならない。
-(2)へ続く-
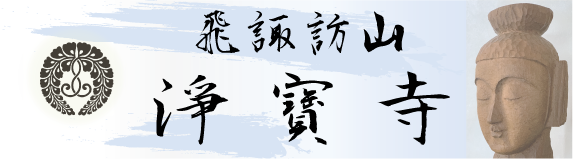





コメント