【淨寶 1928(昭和3)年4月1日発行分】
大無量寿経について(1)ー臼杵祖山ー
経文の文章の完全したものには、大部分、今この大無量寿経の始めにある如く「我聞く是の如し一時仏王舎城耆闍崛山中に住したまい、大比丘衆万二千と倶なりき、一切大聖にして神通已に達せり」等とあります。この中に万二千人の大比丘や文珠普賢弥勒等の菩薩、又、無量無数の方々が集まっていられるような形式が説いてある。こういうような点について、私が考えさせられることは、これは単に釈尊の説法の時処だけにあったことではない、私たちがこうしたお話をさせて頂いている時、又、ただ一人にて念仏愛楽している時も、これと同じ意味が備わっている。経の文句を借りていえば、私一人念仏していれば、そこには必ず万二千の大比丘衆というか、無量無数の菩薩聖衆というか、これらの方々が私一人を中心として、百重千重囲繞して喜び護りたもうのであります。
これについて更にこの経の前後表裏、内容外観を篤と信甞するに、二巻中の始めの大半は阿難尊者を、後の大半は弥勒菩薩を相手として、釈尊はその対告衆一人とただ二人きりの物語で、その他には誰人もいない。万二千人等の文句は、後に経典を編纂する時に当たって、釈尊の徳を讃歎景仰する意味よりして、これを加えたものと味わっても一向に差し支えないと思う。
私はこれを更に押し進めて道味するに、阿難弥勒ということもまた、釈尊お一人の心持ちである。釈尊の御側に二十余年間も奉事していたというこの歴史的阿難を否定するというのではないが、これはただ阿難とは歓喜又は慶喜という意である。大経に説かれたる法蔵比丘の五刧永劫の修行、南無阿弥陀仏の成就、極楽荘厳の尊いこと、これらに対しては誰も歓喜せざるを得ない。即ち釈尊の主観の表現が阿難であり、全く信心の相が阿難である。また弥勒というも、また単なる別人のそれでなくして、釈尊の主観の内容としてであると味わうのであります。丁度釈迦種族の曇悉達多といえるが如く、慈氏の弥勒と言われたもの、慈悲は必ずその一方に悲惨な哀れな光景に対して現れて来るもの、即ち下巻は人間世界の人も家も共に恐ろしい有無の闘諍に没頭している悲惨なる実境が、五悪段を中心として、綿密にしかも組織的に説かれてある。この話相手が慈悲氏の無能勝ー阿逸多ーであった。しかしこれも、あんたと私と話しましょう、というだけのことでなくして、釈尊の慈悲心を開展されたものである。即ち大無量寿経は、釈尊一人の一心の内容を黙然とし、対内的に、しかも尚且つ深刻に、禅三昧食を愛楽された信心歓喜の意趣において相違がある。ここにおいてその相違の点を反省すると同時に、釈尊のそれを愛楽して、釈尊のままを自分自身に取り入れて、これを信甞道味せねばならぬことであります。
私はここに更に意味深く感じますことがある。それはこの阿難相手と弥勒相手との中間に、丁度、蝶番のようになっているのが、「聞其名号 信心歓喜 乃至一念 至心廻向 願生彼国 即得往生 住不退転」等の本願成就文である。これが大経上下二巻を貫通した一心信仰の内容である。この一心から現れた極楽であり娑婆であり仏教界であり人間界である。極楽や地獄があるかないか、もしあれば信ずるが、なければ信ぜずともよい、もしも斯様な心が土台であったならば、たとえあると思うも無いと思うも、共に虚誑迷妄である。そこには「聞其名号 信心歓喜」の蝶番がなければ、ただ左様に思っているだけで地獄、極楽を実際に見ることが出来るのではなしに、ただ経文に左様にある、斯様にあると思っても、それは夢の牡丹餅のようなものにして、決して心の底が中々に承知せないのである。聞其名号信心歓喜乃至一念の見地からでなければ駄目である。また人間の進むべき道を明らかに見せて頂くには、乃至一念至心廻向に由らねば得られない。この一念に立脚して初めて一方極楽荘厳の歓喜の心も、また一方、人間生活の自分の立場がどんな大地に立っているか、全く自分が自分を哀れみ、慈悲をかけずにおれないというこの二つの心は、全く乃至一念の本源から両方に流れ出るのである。この意味で釈尊の信心歓喜の一念が阿難の歓喜ともなり、弥勒の慈悲ともなったのである。そこでこの極楽と人間界、真の仏知見と真の人間味を見出すことは、この乃至一念至心廻向の御恵みである。
ー(2)へ続くー
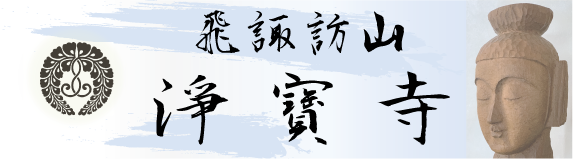





コメント