【淨寶 1928(昭和3)年5月10日発行分】
大無量寿経について(11)ー臼杵祖山ー
左様な点に於いては親鸞聖人は、装うた賢善者でもなく、また飾った愚痴人でもない、畢竟なった愚禿でなくして本来自性愚痴のそのままを信嘗されたのであることが最も尊い味のあることである。これについて私は思い合わさざるを得ないことは、今この大無量寿経に説いてある世自在王仏と法蔵比丘との師弟の物語が非常に尊いことと思います。この法蔵比丘は色々な見方によって味わい方が様々に変わるように思われますが、それらのことは別として法蔵比丘は自分が求める道の上に非常に忠実であられた。言い換えれば道の外に何ものもなかった。道がそれ自身であられたのであると思われます。これについて先ず経文を味わうに、法蔵比丘が世自在王仏の前に於いて自己の心中を色々に陳べられたその中の一節に、
「普くこの願を行じて、一切の恐懼、為めに大安を作さん。たとひ仏ましまして、百千億万、無量の大聖、数恒沙の如くならん。一切これらの諸仏を供養せんより、しかじ道を求めて、堅正にしてしりぞかざらんには」
とあるに見ても、無量の諸仏を供養する道、それも尊いであろうが、しかし法蔵の私一人にとっての一番大切な道は、私一人の道を一心不乱に正しく求めて進むより外には何物もありません、またあってはなりません。法蔵比丘にとっては求道はこれ即ち生命であり自己である。それは法蔵が道を求めるのでなくして、道を求めることが即ち法蔵ということである。私達の習わせは、とかく私があって道を求めると考えるから、いつも道と私が別々に離れてしまうのである。そこで私自身が道を離れた生命なき髑髏に等しく、またいわゆる道そのものも人に離れた空閑なる荒原に同じものと成り果てるのである。法蔵比丘はそんな方ではない。それは道を求めることが即ち法蔵と名のついたわけである。全体法ということは、一事一物に限られた意味のものでなく、一切万法を摂めたものである。仏法では法の一字で一切を顕わす。そこでこの法は一人個人の持ち切りで他に通じないのでなく、また他の限って自分に通ぜぬというものでもない。一切法性、万法などなど、法の一字におさめる、即ち法蔵とは、一切諸法をおさめ、法を離れず、法そのままが比丘の名に顕れたものである。元来人を離れて法もなく、法を離れて人はない。道といい、人といい、また機といい、法といい、一体である。私達の考えは人があって道を行うということになるから、いつも隔てが出来るわけでありますから、畢竟、人もそのものが道でなければならぬ。
「如かじ道を求めてしりぞかざらんには」
と道が生命であられたものが法蔵である。そこで本願は決して客観的に離れたものでなく、いつも私となっている。
「たとひ身は諸々の苦毒の中におくとも、我が行は精進にして忍んで終に悔いず」
我自身が道である。ところが私達はせっかく聞いても、とかく自分そのものになっていない。ただ耳朶に触れるだけである。道を求めることが自分になっていないことが大なる誤りである。
「我をして世において速やかに正覚を成じ、諸々の生死勤苦の本を抜かしめたまへ」
と即ちこの私をどうしましょうか、ということである。それはただ法蔵比丘ばかりではない。いやしくも道を求めるほどの人は常にこの精神である。またあらねばならぬことであります。
孔子が、「これをいかんせん、せんと謂わざるものは吾之をいかんともすること能わず」と我が身中に取入れてないものには、何事であってもどうすることもできないのである。この意味が徹底すれば、この法蔵一人の正覚がきっと成覚して、一切の人に及ぶことは必然である。それはただあの人を救う、この人を救うということでは、却って誰一人救うこともできぬ。太陽は万物を照らし育てようなどといえる考えはない。ただ無心に照らし育てている。彼が無心であればあるほど万物はこれに感謝する。無心に照らし何らほこりがましいことがないから、万物無心に謝して何らそむくことをしないのである。心なしといわれる草木なども、太陽へ太陽へと向かい伸びている。そのありたけが太陽に感謝している相である。しかるに若し太陽が自ら、オレが照らし育ててやるというたならば、却って反抗心を起こし反逆心を起こすであろうに、彼にその事なきがために、これにも従ってその事なく彼此一体になり、天地同根万物一体ともいわるる意味が、彼此の間に顕現するのであります。法蔵比丘が我一人が速やかに正覚を成就し、諸々の生死勤苦をのがれしめたまえと、自己中心の希望と苦痛を訴え述べられた、その時に世自在王仏は、
「修行するところのごとき荘厳仏土、汝自らまさに知るべし」
自分の求めることは自分が知るべき事で、それは外の誰もどうすることもできぬものだと、非常な峻烈なる態度であられたが、これが最も尊い深遠なお慈悲の表現であることを道味されるのである。それに対して法蔵比丘は、
「この義弘深にして我が境界にあらず」
といわれたのである。善導大師や親鸞聖人などの聞くべきことを聞き得ず、信ずべきことを自分にて信じ得ずというその信嘗は、全く今の法蔵の「この義弘深にして我が境界にあらず」との、この淵源から流れているのであることを道味されます。一体に仏法はその根底は自覚である故に、信仰というも自覚であると言われますが、それはなるほど一面には自覚と言える辺はあるが、しかしながら左様に一面観丈を以て仏法全体を味得するわけにはいかない。何故なれば仏法のいわゆる自覚は、自覚とは言いながらも自覚というような凝結をもっていないのである。
「汝自當知」
とお前のことはお前が知れ、お前はお前自身に目覚めなければならぬと言われたるに対して、「それなら目覚めましょう」と言うたかどうか。否、決して左様でない。私は私自分に目覚めようとしてもその力を有しないのであります。たとえば他人の顔は百千万人でも見得られるかも知れませんが、自分自身の目は一生を通じて、否、永遠に見ることのできない悲哀を抱いている自分であります。聞くべき何事をも聞き得ない、信ずべき何事をも信じ得ない、結局自分自身に目覚める力を持たない、愚痴暗鈍にして、これをどうしよう、どうしようと胸をつんざいて苦悶懊悩された方である。普通に私達がなるほどそうですかというような塩梅の目覚め加減とは全く様子が違うものであります。これについて古来、自覚・覚他・覚行窮満を仏陀の三徳と申します。まず自覚せねばならぬ。そうしてそれが自分だけにとどまらず、他をも覚醒せしめねばならぬとする。それは即ち菩薩四大行は自利利他であるというにあるのである。ところがここに私達が最も道破すべきことは覚行窮満であります。この窮満とは自覚して、自覚を徹底し、覚他を脱退して、その全ての相対的差別観念を超越したる霊妙の不思議の境域である。
ー(12)へ続くー
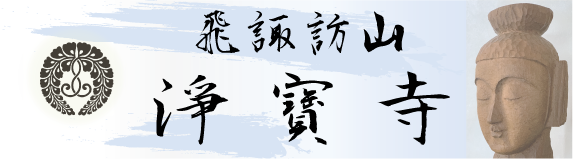





コメント