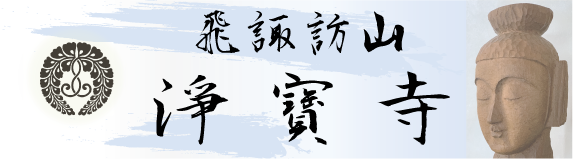管理人ブログ– category –
-

仏教婦人会新年会(H29年)
本日、1月28日、恒例の「仏教婦人会新年会」を開催させて頂きました。 「雪降るぞ~、降るぞ~」と脅かす天気予報をモノともせず、総勢30名、予想外の多数ご参加です。 「新米大統領の過激な発言に世界の注目が集まっています・・・」 とは、会長挨拶。常... -

スリランカ滞在記(38)
スリランカの古都、キャンディに到着した我々一行は、なぜか古都らしからぬ場所、ピザハットの二階へと連れて行かれたのでした。 ガイドさん、どうしてピザハットなんですか? ガ「フフフ、ここからよく見えるネ」 何が見えるんですか? ガ「もちろん、ペ... -

スリランカ滞在記(37)
まだ続いてたの? はい、私の中では絶賛継続中な「スリランカ滞在記」。 中途、番外編「フルーツ体験記」などと、うつつを抜かしたため、八月終盤以来の更新となってしまいました。 と言いつつ正直申せば、スリランカのスの字も思い出すことなく過ごしてい... -

ご報告ー共命鳥行列・太平洋戦争開戦75周年全戦没者追悼法要
前回ブログでご案内させて頂きました通り、先日、12月8日木曜日、「共命鳥行列・太平洋戦争開戦75周年全戦没者追悼法要」を無事修めましたので、ご報告申し上げます。 当日、一番懸念していたことは「お天気」。午後2時に、平和記念公園慰霊碑を参拝... -

共命鳥行列・太平洋戦争開戦75周年全戦没者追悼法要
師走が始まりました。 つい先日まで青空を背景にまばゆく輝いていた銀杏の葉も大方散ってしまい、秋は徐々にフェードアウト、街は本格的な冬を迎えようとしています。 これより、年越しまで様々なビッグイベントが目白押しでありますが、それまでに我々は1... -

報恩講法要
去る、11月16日、一年の中で最も大切な御法要、報恩講法要を50名のご参拝のもと、本年もつつがなくおつとめさせて頂きました。 親鸞聖人は真実のみ教えを明らかにして下さいました。よって、聖人のご命日(旧暦11月28日、新暦1月16日)を機縁として、その... -

東広島河内町 順教寺
昨日、11月7日のこと。 東広島市黒瀬町は徳正寺さんの主催する「伎楽慈音」という雅楽グループの一員として、同じく東広島市河内町の順教寺さんへ行ってまいりました。 順教寺さんはこのたび新たに納骨堂を建立され、その落慶法要における雅楽奏楽のご依頼... -

笛のお伴「聖湖」
突然ですが、ここは北広島町「聖湖」。風一つない湖面は明鏡止水、中央に望む臥龍山が映え、これぞ湖という抜群の景観であります。 カープリーグ優勝パレードで湧いた土曜日の夕方、私は笛の師、福原一間先生にお伴して、ここ聖湖は「正直村」という名のコ... -

釈迦堂(比叡山滞在記)
11月に入り、全国的に寒さが強まってきたようです。特に日本シリーズでカープが優勝するものとばかり思っていた広島の冷え込みようは格別であります。 明日11月5日は、当寺のすぐ近く、平和大通りにて『カープ優勝パレード』が行われる予定ですが、 「リー... -

常行三昧堂(比叡山滞在記)
さて、ここはどこでしょう? ヒント?はい、差し上げましょう。 ヒント①・・・ここは山です。 ヒント②・・・遠望する水面は湖です。 ヒント③・・・ブログタイトルを見て下さい。 ということで、ここは京都・滋賀の県境にまたがる比叡山。天台宗開祖、伝教... -

スリランカ滞在記(36)番外編―フルーツ体験記3
スリランカ滞在記、番外編、フルーツ体験記最終回となりました。 最後を飾るフルーツはコイツです。 と、その前に㊤写真中央部のフルーツ、前回、私はガイドさんにその名称を聞いたものの完全に忘れてしまい、何かピーマンみたいだと、いい加減にやっつけ... -

新住職の辞令
と、ここは京都、「お西さん」こと、「西本願寺」こと、浄土真宗本願寺派ご本山「本願寺」は阿弥陀堂前、9月27日午前5時30分現在。 これから私こと諏訪義円は、ご門主様(言い換えるならば西本願寺の法主)より、住職補任の辞令を頂くのであります。 思え...